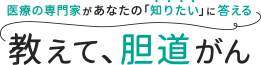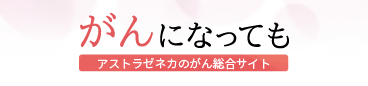日常生活
5. 心の健康

-
父が胆道がんと診断され、大きなショックを受けています。家族として、何か支えになれることはありますか?
どんなに治療が進歩していても、突然のがんの診断は大変ショックなものです。一時的に自暴自棄になったり、やり場のない怒りや悲しみ、不安をご家族にぶつけてしまったりする患者さんもいらっしゃいます。ときには気持ちのすれ違いで、ご家族も傷ついてしまうこともあるかもしれません。
多くの患者さんは、これまで通りの家族でいてほしいと思っています。これまでの関係の延長線上で、患者さん本人が今どのような気持ちでいるかを推し量りながら、心配に思っていること、一緒に治療をサポートしていきたいことを無理のない範囲で伝え、手伝ってほしいことはないかと尋ねてみるとよいでしょう。
そして、ご家族も正しい情報を得ることが大切です。インターネット上の情報についても、信頼できる情報サイトから正しい情報を得て、“病気や治療について正しく知る”ことを心がけましょう。また、患者さん本人の同意を得た上で診察に同席して主治医から治療方針などを一緒に聞くことは、正しい知識を得ると同時に患者さんの心理的サポートにもつながります。
治療方法だけではなく、治療や療養に伴う金銭的な不安や介護の心配などについて、ご家族からも主治医に相談して構いません。患者さんの生活にあった援助を受けられるように病院内のソーシャルワーカーに相談することも可能です。ぜひ、医師、看護師、施設内スタッフにご相談してみてください。

「がん相談支援センター(下記のリンク参照)」では患者さんご本人だけでなく、ご家族の相談にも応じています。どのようにご本人と接したらよいか、支えることができるかなど一緒に考えてくれるでしょう。
-
病気のことばかり考えてしまい落ち込んでしまいます。精神的な面で相談できる所はありますか?
がんによって、体だけではなくこころに大きなストレスがかかり、多くの方がこころのつらさを経験されます。治療の副作用や体の症状によるストレスに加えて、胆道がんの患者さんは治療でチューブなどの器具を体内に入れたまま生活することもあり、そうした状況での生活に対するストレスを感じてしまいます。また、気持ちが落ち込み、将来が不安になり、どうしようもない悲しみや憤りを感じてしまうこともあります。
病院にこころのケアの専門家(精神腫瘍科医や臨床心理士、心理療法士)がいる場合には、主治医を介して診療につないでいただけます。そうした専門家がいない場合には、「がん相談支援センター(下記のリンク参照)」でこころのケアの専門家について相談することもできます。

こころのケアの専門家によるカウンセリングを受けることで気持ちや考えが整理されたり、症状によってはお薬を使って不眠症を改善したり、不安や落ち込みをやわらげることもできるでしょう。一人で抱え込まずに、まずは主治医や看護師に相談してみてください。
<参考文献>
がん研究会有明病院、ほか 編. 胆道がんの治療とケアガイド. 金原出版. 2013年. P102-107.
-
周囲に胆道がんを患った方がおらず、孤独を感じています。同じ病気を経験された方のお話が聞きたいのですが、どこに行けばよいですか?
患者同士の支え合いの場には患者会、患者サロン、ピアサポートなどがあります。同じ病気をした人や、介護を担う患者家族が集まり、当事者同士で交流する機会をもつなどの活動を運営している団体を「患者会」と呼びます。同じ病気の経験をもつ人同士がお互いの悩みや不安を共有したり、情報交換をしたり、勉強会を開いたりしています。また、がん医療の提供体制や治験についてなど、政策提言や社会的なはたらきかけをしている患者会も存在します。
胆道がんでは、複数の患者会があります。いずれの患者会も胆道がん医療の向上や患者の生活の質の向上に役立つことなどを目的に活動しており、胆道がんに関する市民公開セミナーや患者交流会などのイベントも開催しています。

このほか、患者同士の支え合いの場として、患者さんやそのご家族など同じ立場の人が気軽に語り合う交流の場「患者サロン」や、がん経験者(がんサバイバー)が自身の経験を踏まえながら個別に相談を受ける「ピアサポート」なども医療機関や地域の施設で開催されています。また、インターネットで参加できる場(コミュニティ)もコロナ禍で増えてきました。「がん相談支援センター(下記のリンク参照)」でお住まいの近くにそうした交流会があるかどうか、相談してみましょう。
患者同士の支え合いの場への参加は、「悩んでいるのは自分だけではない」と気持ちが楽になったり、ほかの人の体験談を聞くことで悩みを解決するヒントや問題との向き合い方を知ることができたりします。しかし、運営の仕組み、活動の内容は様々で、特色もあります。事前に情報を得たり、実際に参加してみてご自身にとって居心地の良い場を選択することも大切でしょう。
※ここで紹介している患者会などの交流の場については、アストラゼネカ株式会社が推奨しているものではありません。患者さんご自身で、ご自分に合った交流の場への参加をご検討ください。
-
胆道がんと診断されましたが、家族や周囲の人に迷惑をかけたくありません。頼れる相談先はありますか?
胆道がんと診断されてショックを受けることは、無理はありません。そんな時、つらい気持ちを誰かに話すことで気持ちが整理できたり、不安を和らげることができますが、ご家族や親しい方に相談しづらい場合には、主治医や看護師に相談してみてください。主治医や看護師に相談しづらい場合には、「がん相談支援センター(下記のリンク参照)」などに相談することもできます。
また、がん種を問わずに同じ体験をした当事者同士の交流や情報交換をする患者会も各地域にありますので、参加してみるのもよいでしょう。患者会は、同じような経験をした人だからこそ分かち合える「想い」を共有できる場所です。
-
体力的につらい時や在宅療養することになった時は、どのようなサポートを受けることができますか?
在宅ケアには、様々な職種の専門家がチームを組んで対応します。訪問による看護や介護、通院が体力的に厳しい時には訪問診療(定期的な医師の訪問による診療)などの体制に切り替えることも可能です。
在宅ケア:住み慣れた自宅や自宅ではないけれど家に近い住まい(ケアハウスなどの居宅)に身を置きながら療養するのを支えるケアのこと。いつもの生活を、支えられながら自分でできることをやりつつ、必要な医療を外からのサービスで賄うという仕組みです。
介護保険:65歳以上を対象の介護保険サービスが利用できる制度です(病状によっては40歳から64歳までの方の医療保険加入者も対象となります)。ただし、介護保険は事前の申請が必要であり、要介護または要支援状態と認定された場合に利用できます。介護が必要な状態であることが認定されれば、寝たきりでなくても訪問介護、訪問看護、自宅で生活するための必要な福祉用具の貸与などの介護保険サービスを利用することができます。病院だけが治療の場ではなく、日頃からの生活の場である自宅や居宅で、医療のことが分かる専門家とつながりながらゆっくりと療養することが大切です。まずは、地域でどのようなサポートがあるのか、あなたがどのようなサポートを受けることができるかを、事前に「がん相談支援センター(下記のリンク参照)」で情報を得ておくこともよいでしょう。
がん相談支援センター:全国の「がん診療連携拠点病院」「小児がん拠点病院」「地域がん診療病院」に設置されている、どなたでも無料・匿名で利用できるがんに関する相談窓口です。がん専門の看護師やソーシャルワーカーが治療や生活、就労などに関する様々な相談に乗ってもらえます。
訪問看護:看護師が自宅訪問し、患者さんの看護ケアや健康管理などを行うこと。訪問看護を提供する施設を訪問看護ステーションと呼びます。
地域包括支援センター:介護予防を含めて、在宅療養などに関するさまざまな制度の利用や福祉の相談・支援を行っており、各市区町村に設置されています。
ケアマネジャー(介護支援専門員):介護保険にて要介護認定を受けた人やそのご家族からの相談に基づき、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、計画実施に関する連絡・調整などを行います。

<参考文献>
がん研究会有明病院、ほか 編. 胆道がんの治療とケアガイド. 金原出版. 2013年. P140-145.
監 修
神奈川県立がんセンター
総長 古瀬 純司、がん相談支援センター 得 みさえ
それぞれのお問い合わせ先にご連絡ください。
「教えて、胆道がん」は
その第三者のサイトの内容等についての
責任は負いかねますのでご了承ください。